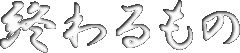「俺とおまえの進む道は違う。目的も、信念もどれを引き合いに出しても。だから――同じ道を同じ目線で見据えては進めない」
「一緒には行けないって事ですか」
「……――ああ」
「覚悟はしてました。もちろん、あなたを頼りにしていた訳じゃないし、私もあなたがいると仕事が上手くいかないからっていう事もありますけど。じゃあここでお別れですね」
腰まで届く海を映したような色の髪を風になびかせる姿は凛々しい。そして儚げでもあった。
少女はさっぱりとした口調で「あ、そうだ……」と何かを思い出したように言葉を続けた。
相手にとって重いしこりとならないように、そして何より自分にとっても希望の芽とならないように。
ふした瞼(まぶた)をゆっくり持ち上げて、自然な笑みが浮かべていることを意識して。
「もしも……、この広い海で再び巡り会う事ができたなら、その時は…………」
「■■■■■■■■■■■■■■■」
「■■■■■■■■■■■■■■」
あの時。
恋焦がれた女の言った言葉が思い出せない。
それに対して自分が返したであろう返答も。
あんなにも求めたのに。
――あの藍色の髪を、声を、瞳を、全てを。
あんなにも恋焦がれたのに。
――持っているものをなげうってでも。
そしてあんな後悔は2度としたくねェ、そう思った。
だけど――
その感情が強すぎて言葉が記憶の中から薄らいだ。
あの時言えなかった思いが、言葉が、感情が。
色々な足りなかったものが、今なら言える。そんな気がする。
なぜなのだろう。問題を忘れたのに証明や定義をすっとばして、しどろもどろしながらでも答えが出せる気がする。例えるならそんなイメージ。
「ゾ……ロ……。ゾ……ロ。ねえ、ゾロ」
揺らぐ意識は控えめにかけられた声で夢の狭間から現(うつつ)へと急速に引き戻された。
重い瞼(まぶた)を瞬(しばた)いてゾロと呼ばれた男は心配そうに顔を歪(ゆが)ませる女を無言で見つめた。
ゆっくりと腕を持ち上げて肩のラインでくるりとはねている女の髪の毛を撫(な)でる。闇夜であっても輝かしいオレンジ色の髪の毛の感触を手で楽しみながら、それと同時に安堵(あんど)した。
(夢じゃねェ。手が届く)
「な、なに? 髪の毛がどうかした?」
「いや、なんでもねェ。でも……もう少しこのままでいてくれ」
普段甘えた言葉を口にしないゾロが珍しく甘えた声をあげた。その事にオレンジ色の髪の持ち主――ナミは「珍しい事もあるのね」と思いつつ、されるがまま、時は過ぎていった。
2006年ナミ誕生祭小説その壱
「今日は有り難う、すごく嬉しかった!」
未だ興奮冷めやらぬ雰囲気の中、この日の主役、ナミがジョッキ片手に月へとグイと付きあげてクルーの仲間にお礼を言った。
皆は口々に「お誕生日おめでとう!」と再び場を盛り上げる。そして終わりの挨拶、してまた「おめでとう」コールを繰り返す。そんなバカ騒ぎももう何度目だろうか。そろそろ真夜中という時間だったが彼らに縛られる時間の概念などなかった。
今日は大事な航海士の誕生日なのだ。盛大に祝って、飲んで、踊って、歌って、騒いで。
ナミはお腹がよじれるかと思うほど眼に涙を浮かべて笑った。
また太陽が顔を覗かせる頃になって、さすがの麦わらのクルー達もイビキをかいて寝始めた。
けれどただ独り眠れない女がいた。
今日の主役、ナミだ。
酒を浴びるほど飲んだのにもかかわらず、少しも酔ってはいなかった。パーティーが開始されてからずっと――太陽が沈み月が真上に昇っても――ジョッキを手放さなかったが酔わなかった。いや、酔ってはいるだろうが酒を飲めば飲むほど頭が冴(さ)えて酔えなかったというべきか。
自分でも酒豪だと自負しているし酒に飲まれた事もない。酒を飲む時どんな感じかと問われれば、感覚が研ぎ澄まされる、とでもいうのだろうか。酔った事がなかったからナミにはわからない。
それに今夜はより一層、これからの行動も考えればこそ、意識が冴えたのかもしれない。
先ほどまでニコニコと上機嫌だったナミは表情を一変させ、口の端を結び奥歯を噛みしめた。顔からは笑顔が消えどこか暗い。
それでも重い腰をあげて、甲板の上で仰向けになっているクルー達1人ずつ寝ているかどうか、顔を覗きこみ確認してまわった。最後の剣士の所まで辿り着くと特に念を入れて確認する。ジロジロと穴が空くほどに。
ナミと同様に剣士であるゾロはめっぽう酒に強く、いわゆる酒豪だ。油断はならない。寝ている振りをしているかもしれない。
息を殺して忍び足で近づくときっと身体の動きが硬くなって逆にゾロに気づかれかねない。だから自然体で近づく。
すると、ゾロはぐっすり寝ていた。杞憂に終わってホッとするナミだったが、ゾロと真正面から向き合ってみると、これからナミが起こそうとしてる事が自分が思った以上に辛い事なのだと実感せずにはいられなかった。
膝(ひざ)を両手で抱えて座りこむ。そしてジッと食い入るように、記憶に刻みつけるようにゾロの顔を見つめた。
寝ている男にかけられる声はか細く、涙声。
「きっと怒るわよね、あんた。でも、これが最善だと思うから。私は平気だから。アーロンパークで、そしてそれ以前にも守ってもらったのには本当に感謝してる。だから、今度はわたしがあんたたちを守るわ」
恐れているようで、それでいてきっぱりと決意を表した声。
言いたい事を述べたあとは、もう、涙は止まっていた。
「行くのか?」
唐突にかけられた声に身体がビクリと跳ねる。が、相手の姿を確認できたおかげで息を整える事ができた。
「ルフィ……。驚かさないでよ」
「行くのか?」
「ええ、この事については詳しく話し合ったでしょ? 暫く私に時間を欲しいの。必ず帰ってくるから」
「…………」
ね、ほら顔をあげて。とまるで子供をあやす様にナミは優しくルフィに声をかける。
「…………」
それでもナミの行動に不満があるのかルフィはぶすりとしたままだ。
このまま相手の機嫌を窺(うかが)ってばかりもいられない。時間が迫っているのだ。
ナミはニッコリと微笑んで、
「じゃあね、行ってくるわ」
サッと手すりを乗り越えて――いつの間にやら用意していたのだろうか――小船に乗り移ると、ナミは一度も振り返らず事無くゴーイングメリー号を後にした。
去って行ったナミの後姿をただただ見つめて、ルフィは最後まで無言で見送り続けた。
つづく