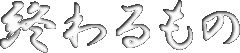「ちょっと、高いんじゃない? あんたとこ。こんど上げたらもう買わないからね」
垂れ目のカモメが困ったようにクィーと鳴いた。人の言葉こそ喋(しゃべ)りこそしないものの、その表情から見て、「そんな事言われても」と言っているかのようだ。
ナミとカモメのやりとりを作業しながら耳に捉えたウソップはついと気になった事を口にした。
「おい、ナミ。前にも同じ事違うカモメール――新聞屋――に言ってなかったか? もしかして新聞代ぼったく――……グハッ。イテーー!」
一撃必殺(いちげきひっさつ)。
ナミの拳(こぶし)は今日も好調のようだ。実にキレがよい。
「なにか言った? 私がぼったくってるなんのって。前にも言ったでしょ、毎日とってたら新聞代もばかにならないのよ」
「すみませんでしたァ!」
辛うじて言葉にできたのはそれだけで、頭から血を流し、目は恐怖の色を浮かべながらウソップはどこかへ逃げるように行ってしまった。
ツッコミ役もいなくなった所で、ナミは耳に手を添えて耳をすませる。何か問題でも起こればおちおち新聞も読めやしないからだ。
するとキッチンからだろうか、つまみ食いをする船長とそれを阻止(そし)すべくコックの言い合いが聞こえてきた。
よし、この調子なら暫く時間稼(かせ)ぎになるわね。そう思うと次に目を転じて残りの仲間を探す。
すぐ傍、と言っても視界にギリギリ収まるかどうかの位置にグガー、ぐおー、とイビキをかいているゾロはあいも変わらず、ナミとの適度な距離に陣取って寝こけている。
4人目確認と――次は。
またキョロキョロと辺りを見回す。
マストのてっぺんを見上げると、双眼鏡を必死に覗(のぞ)きこむ帽子が見える。ジーっと動かないかと思うと急にビクリとしたように突然動き出す。ピョコピョコした帽子の動きがなんとも可愛らしい――チョッパーは今見張りについているようだ――、ロビンは何だか朝からずっと難しい本を黙々と読んでいる。
これなら心配いらないわね。暫くは皆別々の事に夢中でナミに構いやしないだろう。
久しぶりにゆっくり新聞が読める。何気ない日常がとても嬉しい。
だが、新聞には胸を弾ませて読むような内容ばかりではない。内戦、紛争、海賊同士のいざこざ――時には一切新聞を読みたくなくなる日もあったが、情報に疎(うと)くては世の流れについてけない。
情報を掴めれば時機を見分けるヒントになるやもしれない。知っていて損になることはないだろう。そう思うからこそナミは毎日新聞に目を通す。
と、その前に一仕事残っている事を思い出した。
透明な球体を覗きこんで航路を確認する。記録指針(ログポース)は順調に真っすぐ未だ見えぬ島をさしていた。
肌に感じる心地よい風を受けながら「うん、前みたいな嫌な感じはしないわ」と言うと、チェアーに身を沈めて新聞を広げた。
ハラリ――
と木の葉が舞い散るように、新聞の間から1枚の紙がデッキにふわりと落ちた。
以前にも似たような時があったわね……と思いつつ、ナミは手に取った。
「………………どうして」
あまりの驚きように言葉が続かないナミは、ただただ手元の紙をクシャリと歪むほど握(にぎ)った。
ナミが手にしているのは手配書。
世界政府から新しく賞金をかけられた証であるもの。言い換えるなら、世界政府から悪だと認識された証拠だとも言える。
そこに写っているのは紛れもないナミ自身――
デッド・オア・アライブ――生死問わず。
賞金五千万。
いつ撮られたのだろう、記憶にない険しい顔をして写っている自分をナミは凝視(ぎょうし)するより他なかった。
――――これが、ナミがゴーイングメリー号を去る10日前の出来事。
散りばめられたパズルのピースは元々あったのだ。
ただ、枠(わく)が無かっただけ。
いま、静かにナミの元に手配書という枠が揃(そろ)った。
後は、パズルを完成させるだけ。
「さあ、仕上げといこうか」
愉しそうに、男はニタリと卑(いや)しく笑う。
2006年ナミ誕生祭小説その弐
「どうして――? どうしてこのタイミングで手配書が出されるのよ」
今は空島から頂戴してきた黄金を換金する為に記録指針(ログポース)が指し示す次の島への航海中で、地上では政府の目にとまるような事はしていない。
そう、地上では。
アラバスタでの歴史に名を残さない戦いの後、ルフィが元々ルーキーにしては破格であった賞金の額を更にあげた。そしてゾロも――遅かったと言っていいが――賞金がかかった。
アラバスタで麦わら一味の活躍を、その意義を知っていたなら、全員に賞金をかけるのが妥当だ。
だが言うなれば、結果麦わら一味からは2人しか賞金がかけられなかった。
その時点でゾロと同様にナミにも賞金がかけられたなら、嫌だと叫びながらも納得する事ができただろう。
事の重要性を海軍が重く受け止め一見ひ弱な航海士にまで賞金をかけた。
――――というように。
しかし、時期が違う。流れがわからない。ジャヤ島でのベラミーとのいざこざ。この件に関してはナミは全く無関係とは言えないまでも、アラバスタほど深くかかわった覚えはない。
ではジャヤでのいざこざは賞金がかけられることに関係はないといえる。
その後は空島での戦いだが――
それこそ地上にいる海軍、世界政府に知られることはないはずだ――悪魔の実の能力で知られていれば話は別だが。
記憶の糸をたどって、ナミは机に肘(ひじ)をつき手で頭を支えて考えていた。
「どうして、地上での航路を再開した途端に手配書が出るの? おかしいじゃない。
それとも――ただの考えすぎ?」
疲れが出たのだろうか、今まで張りつめていた糸がプッツリと切れたようでどこか安心している気がする。
今まで戦い続きだった日々に、目に見えてお宝という黄金を手にしたのだ。舞い上がっていない、などと言えなくもない。
「あっ! ……もしかして海軍大将の青キジの仕業? ――でもそれが一番可能性が高いわね」
突然脳裏に以前フォクシー海賊団との勝負の後出遭った海軍大将の事をナミは思い出していた。
『……これまでにお前達のやってきた所業の数々――その成長の速度……長く無法者達を相手にしてきたが末恐ろしく思う……!!!』
と、確かに青キジは言った。
あいつならば世界政府にもっとも繋がりのある人物だと言えるし、早急な手配書を作る事も可能だろう。
けれど、
「違うわ」
ナミが口に出した答えは違った。
何かが引っかかる。
違うと――そう思った。
確かに海軍大将青キジは麦わら海賊団の存在を、そして、その先の姿を軽んじてはいなかった。
ならば、どうしてナミ独りだけ手配書が回ってきたのだろう。
どうして麦わら全員の手配書が配られなかったのだろうか。
ナミの疑問はそこに続いていた。手配書が配られるきっかけとして一番に浮かぶのは青キジ、けれどあいつならば全員の手配書を配らせただろう。
その根拠として、あの場所にいて直接戦闘にかかわったサンジを手配書に加えないという事は考えられない。ナミ達にとってメリットになろうとも、海軍にとってはデメリットでしかないのだから。
何より賞金の金額が破格ではないだろうか。
グランドラインで航海してるからだろうか、いや、そんな基準ではないはず。航海士に五千万の値をつけるとは――
海軍の思惑が見えてこない。
これでは当分自分に賞金がついたなどと言えるはずもない、とナミは頭が重い気がした。
「おっ、なんだ。ついにおまえも賞金首ってか」
突如(とつじょ)耳元で楽しげな声が響いた。
耳にかかる心地のよい声だったが、いきなりだった為にゾロはナミからゲンコツ返しというしっぺ返しにあってしまった。
「び、びっくりするでしょ。もう、脅かさないでよ、バカ」
「いてっ! 本気で殴ることねーだろうが。ったく」
しゃがみこみ両手でつい先ほどできたたんこぶを労わるようになでながら、ゾロは涙目になりながら上目遣いでナミに抗議した。だが、ナミは目力を強くして、有無を言わせない言葉で言い放った。
「手配書の事は誰にも言わないように。黙ってて、わかった?」
「……あ、ああ」
つづく